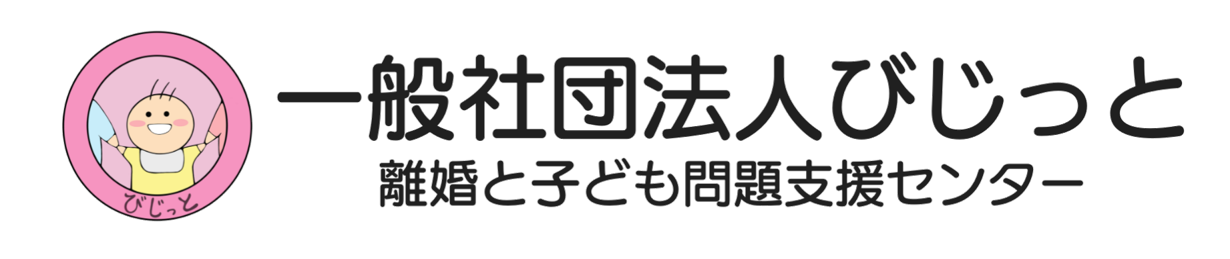利用者アンケート調査結果(2024)
2025年3月11日
昨年に引き続き、びじっと利用者アンケートをおこないました。
昨年と同様、親子交流支援を利用される前に利用者さまが抱えていた不安が、支援利用後は大幅に低減されていることが分かりました。また、同居親の方が親子交流を意識するタイミングが早い傾向にありました。
引き続き、びじっとはこれからも、親子交流および親子交流支援の認知促進と、よりよい支援の提供に努めてまいります。
調査方法
- 実施期間:2024年10月16日~2024年10月31日
- 実施方法:Webによる無記名アンケート
- 対象者 :びじっと支援利用者:354名
- 回答者 :同居親60名、別居親46名(※同居親兼別居親は両方として):計106名
- . 利用者アンケート調査結果(2024)
- 1. 【1】はじめに、親子交流支援を受けたきっかけについてお伺いします。
- 1.1. 1-1.親子交流を初めて認識したのは、どのタイミングですか?(必須・単一選択)
- 1.2. 1-2.親子交流について、どこで/誰から情報を得ましたか。(必須・複数選択)
- 1.3. 1-3.親子交流の実施を初めに提案したのは、どちらですか。(必須・単一選択)
- 1.4. 1-4.親子交流支援団体(びじっと以外も含む)の利用を初めに提案したのは、どちらですか。(必須・単一選択)
- 1.5. 1-5.親子交流支援団体(びじっと以外も含む)について、どこで/誰から情報を得ましたか。(必須・複数選択)
- 1.6. 1-6.支援内容の確認後、すぐに利用してみようと思いましたか。(必須・単一選択)
- 1.7. 1-7.支援の利用に際し、どのようなことが気がかりでしたか。(必須・複数選択) 1-8.支援利用してみて現在も気がかりなのは、どんなことですか。(必須・複数選択)
- 1.8. 1-9.親子交流支援にかかる費用は、どなたが支払っていますか。(必須・単一選択)
- 1.9. 1-10.あなたが親子交流をおこなう理由をお聞かせください。(必須・複数選択)
- 1.10. 1-11.親子交流は「子どもの権利」であることを、どこで/誰から知りましたか。(必須・複数選択)
- 2. 【2】次に、親子交流の状況についてお伺いします。
- 2.1. 2-1.あなたはびじっとの支援を利用して何年目ですか。(必須・単一選択)
- 2.2. 2-2.あなたの交流対象のお子さんの年齢をお聞かせください。(単一選択)
- 2.3. 2-3.あなたが現在利用している支援型をお聞かせください。(末子の年齢)(必須・複数選択)
- 2.4. 2-4.現在の、一回あたりのおよその交流時間をお聞かせください。(単一選択)
- 2.5. 2-5.現在の、年間あたりのおよその交流頻度をお聞かせください。(単一選択)
- 2.6. 2-6-1.親子交流を開始して、お子さん自身に良い変化はありましたか。(必須・単一選択)
- 2.7. 2-6-2.親子交流を開始して、お子さん自身に心配な変化はありましたか。(必須・単一選択)
- 2.8. 2-6-3.親子交流後に、お子さんにあった良い変化あるいは心配な変化について、具体的にお聞かせ下さい。(自由記述)
- 2.9. 2-7.お子さんが成人した時、別居親さんとお子さんがどんな関係になっていれば良いなと思いますか。(自由記述)
- 2.10. 2-8.これまで支援を受けて感じたことについてお聞かせください。 2-8-1.これまで支援を受けて良かったことはありましたか。(必須・単一選択)
- 2.11. 2-8-2.これまで支援を受けて嫌だったことはありましたか。(必須・単一選択)
- 2.12. 2-8-3.良かった点、嫌だった点をお聞かせ下さい。(複数選択)
- 2.13. 2-9.びじっとの支援内容について、あなたの評価をお聞かせください。(必須・単一選択)
- 2.14. 2-9-3.上記のように評価した理由をお聞かせ下さい。(自由記述)
- 2.15. 2-10.びじっとが現在提供している、紛争解決のための支援「ADRくりあ」をご存じですか。(必須・単一選択)
- 2.16. 2-11.びじっとが現在提供しているraeru見守り型をご存じですか。(必須・単一選択)
- 2.17. 2-12.以下の項目の中で、もしあれば利用したい支援はありますか。(複数選択)
- 2.18. 2-13.現在の支援型、交流時間および頻度の変更についてお伺いします。 2-13-1.支援型について(必須・単一選択)
- 2.19. 2-13-2.交流時間について(必須・単一選択)
- 2.20. 2-13-3.交流頻度について(必須・単一選択)
- 2.21. 2-13-4.親子交流の支援型や時間・頻度の変更希望について、その理由をお聞かせください。(自由記述)
- 2.22. 2-14.あなたが支援卒業やステップアップをする場合、どの要素が検討ポイントになりますか。(必須・複数選択)
- 2.23. 2-15.びじっとの支援をより良くするために、あなたのご意見をお聞かせください。(自由記述)
- 3. 【3】最後にあなたについてお伺いします。
- 3.1. 3-8.あなたの性別を教えてください。 交流対象のお子さんと、同居/別居について教えてください。(必須・単一選択)
- 3.2. 3-7.お子さんの親権はどちらが保持していますか。(任意・単一選択)
- 3.3. 3-2.あなたの年齢を教えてください。(任意・単一選択)
- 3.4. 3-3.あなたの居住地を教えてください(任意・単一選択)
- 3.5. 3-4.あなたの最終学歴を教えてください。(任意・単一選択)
- 3.6. 3-5.あなたの現在の職業を教えてください。(任意・単一選択)
- 3.7. 3-6.あなたの世帯年収について教えてください。(2022年の概算・税引き前)(任意・単一選択)
- 3.8. 3-9.あなたが同居している方について教えて下さい。(任意・複数選択)
- 3.9. 3-10.あなたは養育費を受け取っていますか、それとも支払っていますか。(任意・単一選択)
- 3.10. 3-11.あなたが支払っている/受け取っている養育費を月額で教えて下さい(任意・単一選択)
- 3.11. 3-12.最初に別居・離婚を申し出たのはどちらからでしたか。(任意・単一選択)
- 3.12. 3-13.どのような方法で離婚が成立しましたか(任意・単一選択)
- 3.13. 3-14.別居・離婚直前のあなたの収入は、世帯収入のどの程度を占めていましたか。およその割合(%)を教えてください。(任意・単一選択)
- 3.14. 3-15.別居・離婚直前のあなたと相手の一週間あたりの家事分担について、あなたのおおよその分担割合(%)を教えてください。(任意・単一選択)
- 3.15. 3-16.別居・離婚直前のあなたと相手の一週間あたりの育児分担について、あなたのおおよその分担割合(%)を教えてください。(任意・単一選択)
【1】はじめに、親子交流支援を受けたきっかけについてお伺いします。
1-1.親子交流を初めて認識したのは、どのタイミングですか?(必須・単一選択)
同居親の方が早いタイミングで、親子交流を意識していることがわかります。


1-2.親子交流について、どこで/誰から情報を得ましたか。(必須・複数選択)
情報入手は弁護士・インターネット、次いで家裁の順番です。

1-3.親子交流の実施を初めに提案したのは、どちらですか。(必須・単一選択)
親子交流の提案は別居親からが多いですが、同居親からの提案もかなりの数を占めます。

1-4.親子交流支援団体(びじっと以外も含む)の利用を初めに提案したのは、どちらですか。(必須・単一選択)
支援団体の利用は、同居親の方が積極的です。

1-5.親子交流支援団体(びじっと以外も含む)について、どこで/誰から情報を得ましたか。(必須・複数選択)
情報入手は弁護士・インターネット、次いで家裁の順番です。

1-6.支援内容の確認後、すぐに利用してみようと思いましたか。(必須・単一選択)
支援団体の利用は、同居親の方が積極的です。


1-7.支援の利用に際し、どのようなことが気がかりでしたか。(必須・複数選択)
1-8.支援利用してみて現在も気がかりなのは、どんなことですか。(必須・複数選択)
同居親・別居親ともに支援前は多くの心配を抱えていましたが、支援開始後は不安が激減していることがわかります。ただ「いつ卒業できるか」の心配だけは減っていません。

1-9.親子交流支援にかかる費用は、どなたが支払っていますか。(必須・単一選択)
費用は折半のケースが比較的多いです。

1-10.あなたが親子交流をおこなう理由をお聞かせください。(必須・複数選択)
どちらの親も「子どものため」を第一に考えています。

1-11.親子交流は「子どもの権利」であることを、どこで/誰から知りましたか。(必須・複数選択)
情報入手はインターネット・弁護士、次いで家裁の順番です。

【2】次に、親子交流の状況についてお伺いします。
2-1.あなたはびじっとの支援を利用して何年目ですか。(必須・単一選択)
5年以上支援を受けている方も多くいらっしゃいます。

2-2.あなたの交流対象のお子さんの年齢をお聞かせください。(単一選択)
小学生、幼児が多いですが、中学生のお子さんもいらっしゃいます。


2-3.あなたが現在利用している支援型をお聞かせください。(末子の年齢)(必須・複数選択)

2-4.現在の、一回あたりのおよその交流時間をお聞かせください。(単一選択)
3時間までの交流が6割を占めますが、長時間交流もおこなわれています。


2-5.現在の、年間あたりのおよその交流頻度をお聞かせください。(単一選択)
年間12回(月1回)の方が多いですが、少ない頻度の方もいらっしゃいます。


2-6-1.親子交流を開始して、お子さん自身に良い変化はありましたか。(必須・単一選択)
良い変化を感じた方が、平均して半分強。別居親の方が良い変化を感じています。


2-6-2.親子交流を開始して、お子さん自身に心配な変化はありましたか。(必須・単一選択)
心配な変化を感じた方が、平均して半分強。同居親の方が心配な変化を感じています。


2-6-3.親子交流後に、お子さんにあった良い変化あるいは心配な変化について、具体的にお聞かせ下さい。(自由記述)
親子交流を通じて親子関係が良好になったという良い面と、交流前後に子どもが不安定になったという心配な面があげられています。
代表的なものを紹介します。
同趣旨回答の数を同居親、別居親ごとに[同*別*]と記載します(以後同表記)。
■良い変化
- 別居親がいるという事や別居親の愛情を認識できた [同7別3]
- 交流中の別居親の他人へのふるまいを見て子どもながらに何かを感じ取ってくれ、父母の関係を客観的に見ることができるようになった[同1]
- 婚姻関係にあった時は父親と遊ぶ機会が無かったが、今交流することで楽しく遊べている[同1]
- 同居親に言えないことを交流中に言うなど、良い意味で甘えるようになった[別1]
- 別居親をオヤジと呼び慕っている様子が見られること[同1]
■心配な変化
- 子どもが交流前後に、体調が悪くなる[同3]
- 交流中の別居親の言動に戸惑い、別居親の極端な考え方に影響を受けたり、精神的に不安定になる[同6]
- 別居親に欲しい物を言えばすぐにその場で買ってもらえるため、物やお金を大事にしなくなった [同1]
- 成長するにつれ、親子交流を嫌がることが出てきた[同1]
2-7.お子さんが成人した時、別居親さんとお子さんがどんな関係になっていれば良いなと思いますか。(自由記述)
子どもが別居親に悩み事などを相談できる関係になれれば、と考えている方が多いです。
代表的なものを紹介します。
【別居親に悩み事を相談するなど頼ることのできる関係 [同7別4]】
- 子どもが困った時に頼れる存在になってもらえたら良いなと思っています。[同]
- 自分(同居親)には相談しにくいことに対して、気軽に相談できるような相手になっていてほしい。[同]
- 同居親の死後、遠慮や躊躇なく頼れる関係になっていてほしい。[同]
いつでも子供が望むときに会える関係[別]
【普通の親子関係 [同2別5]】
- 一般的な父親と子供たちのように、何でも話せたり、相談できるような関係でいたいです[別]
- 変わらず親子関係を築いていてくれれば良いと思う[同]
- 親子の深い絆がある信頼関係[別]
【別居親に自由に会える関係 [同4別9]】
- 親同士が中間に入らなくても自由に会えるようになったら良いと思う。[同]
- お互い会いたい時に気軽に連絡をとって自分で会える。[同]
- 親子でお互い会いたい時に会える[別]
- 同居親に気兼ねなく、別居親と会える関係[別]
【適切な距離をとれる関係 [同6別1]】
- 子どもが望む適切な距離をとれるようになってほしいです。[同]
- 別居親が、子供は独立した一人の人間である事を理解し、子供の人生・意思を尊重していて欲しい。[別]
- 本人の意思ではあるが子供が傷つかないような関係性であって欲しい。[同]
【別居親と交流がない関係 [同10別1]】
- 虐待、暴力、DV、傷害があったので会いたくないと言っているし会わないと思う。[同]
- 子ども達にお金を請求するなど悪影響を与えそうなので、完全に縁を切ってほしい。[同]
2-8.これまで支援を受けて感じたことについてお聞かせください。
2-8-1.これまで支援を受けて良かったことはありましたか。(必須・単一選択)
同居親の83%、別居親の78%が「良かったことがあった」と感じています。


2-8-2.これまで支援を受けて嫌だったことはありましたか。(必須・単一選択)
同居親の42%、別居親の54%が「嫌だったことがあった」と感じています。


2-8-3.良かった点、嫌だった点をお聞かせ下さい。(複数選択)
「良かった点」としては、親子交流の実現、父母の精神的負荷軽減があげられています。「嫌だった点」としては、支援料金の高さ、担当者の不均質性があげられています。

2-9.びじっとの支援内容について、あなたの評価をお聞かせください。(必須・単一選択)
支援開始前~支援に関しては比較的満足度が高いですが、支援料金に関しては満足度が下がっています。


2-9-3.上記のように評価した理由をお聞かせ下さい。(自由記述)
【満足】
- 親子交流ができている[同1別3]
- 相手方と連絡をとらないで済むのは助かる[同3]
- シンポジウムなども開いてくれるので勉強になります[同1]
- 連絡調整支援の時に、とても丁寧に親身になって対応して下さいました。安心して面会交流の連絡をして頂けて心より感謝しております[同1]
- 料金は高いけど支援員が一緒に子供の遊び相手をしてくれてよかったです [別1]
- ホームページで事前に知りたい情報を得ることができた[同1]
- 支援方法やルール、支援員の方々の対応には満足しています[別1]
- すごく込み入った調整になる際も粘り強く対応してくださって、本当に助かりました。それを自分で対応することを考えると費用はお安いと思います[同1]
【不満】・・・支援による制限
- 交流時の子どもとの買い物の金額制限が1,000円以内では、お祭り等に一緒に行った時に、子どもがやりたいことが著しく制限されてしまいます[別1]
- 付添い型だと家族(祖父母など)に会わせられない規約になっている[別1]
【不満】・・・支援料金
- 助成金などが無く支援料金が高くなるのは仕方ないですが、養育費を支払い本当にカツカツで生活している別居親にしてみると、支援料負担がきつく、お金が払えなくなれば子供たちとも会えなくなってしまう、という不安があります[別1]
- 請求書の不備(間違えられた、届かなかった)[同1別2]
【不満】・・・親子交流(面会交流)の合意条件自体に不満
- 相手方が面会拒否をしているため一年ほど子どもと会えていない[別1]
- 支援内容は同居親のいいなり[別1]
【不満】・・・スタッフに対する不満
- 付添いスタッフの服装や態度が良くない[同1別1]
- 日程調整で間違いがあったり、調整がうまく進まないことがあった[別1]
- 受理面談を担当者が忘れて実施できなかった[同1]
2-10.びじっとが現在提供している、紛争解決のための支援「ADRくりあ」をご存じですか。(必須・単一選択)
紛争解決支援「ADRくりあ」を知っている人は約8割でした。


2-11.びじっとが現在提供しているraeru見守り型をご存じですか。(必須・単一選択)
aeru見守り型を知っている人は3割程度でした。


2-12.以下の項目の中で、もしあれば利用したい支援はありますか。(複数選択)
費用助成と親子交流個別相談は父母双方から求められています。ADRの費用助成を求める方もいらっしゃいました。また、ステップアップ支援や子育てについてもニーズが高いです。

2-13.現在の支援型、交流時間および頻度の変更についてお伺いします。
2-13-1.支援型について(必須・単一選択)
別居親から「より軽度の支援への移行」希望が多くあります。


2-13-2.交流時間について(必須・単一選択)
交流時間の長さは、同居親・別居親の間で希望がわかれています。


2-13-3.交流頻度について(必須・単一選択)
交流頻度は、同居親・別居親の間で希望がわかれています。


2-13-4.親子交流の支援型や時間・頻度の変更希望について、その理由をお聞かせください。(自由記述)
【より軽度な支援へのステップアップを希望】
- 子どもも大きくなり直接連絡して面会が実現できる段階のため[別1]
- 子供に任せたい。同居親に遠慮なく実施してほしい[同1]
- 費用の都合で付き添い型から受け渡し型にしてもらえるといいです[別1]
【交流を減らしたい】
- 子どもは成長すると(部活などで)忙しく、親とは外出したがらない[同6]
- 子が別居親との面会交流を少なからずストレスに感じており、時間も頻度も増やすのはまだ難しそうである[同1]
- 子ども達が別居親に会うことを希望していない [同1]
【交流を増やしたい】
- 子どもがもっと会いたがっていて、私自身も会いたい[別3]
- 現状が少なすぎる、短すぎる、会えていない[別4]
- 春夏冬休み等の長期休暇中は、もう少し長い宿泊面会を実施したい[別2]
【現状維持を希望】
- 料金が高いので回数や時間を増やせられない[同1別2]
- 子どもが心療内科に通院中のため、負担を大きくしたくない[同1]
- 判決などで決めたこと[同2]
2-14.あなたが支援卒業やステップアップをする場合、どの要素が検討ポイントになりますか。(必須・複数選択)
子どもの年齢を見ながら子どもの要望に沿いたいという意見が多くありました。

2-15.びじっとの支援をより良くするために、あなたのご意見をお聞かせください。(自由記述)
- (子の年齢や状況に合わせた)ステップアップの仕組みを作って欲しい[同1別3]
- 父母の間に入っていて大変だと思うので、支援スタッフのケアをしてほしい [同2別2]
- 料金が高いので、行政からの補助金等の支援があると良い [同1別2]
- 支援スタッフを固定してほしい[同1別1]
- 子どもと二人だけの時間もつくりたい[別1]
- 日程調整がすすむように「2週間前までに確定させてください」などやや厳しめのルールを作って欲しい [同1]
- 「ADRくりあ」より相談しやすい悩みにも対応できるようなものがある助かる[別1]
- 本契約の付添い型の料金設定を1時間単位にしてほしい[別1]
- 付添い型では祖父母など他の家族に会わせられないことです。もう10年会わせられていません。祖父母にとっても本当に悲しいことです [別1]
- 付添い型はスタッフ2名が必須なことが不満[別1]
- びじっとがなければ、面会交流できませんでした。とてもありがたい存在です。[同9]
【3】最後にあなたについてお伺いします。
3-8.あなたの性別を教えてください。
交流対象のお子さんと、同居/別居について教えてください。(必須・単一選択)

3-7.お子さんの親権はどちらが保持していますか。(任意・単一選択)

3-2.あなたの年齢を教えてください。(任意・単一選択)

3-3.あなたの居住地を教えてください(任意・単一選択)

3-4.あなたの最終学歴を教えてください。(任意・単一選択)


3-5.あなたの現在の職業を教えてください。(任意・単一選択)


3-6.あなたの世帯年収について教えてください。(2022年の概算・税引き前)(任意・単一選択)


3-9.あなたが同居している方について教えて下さい。(任意・複数選択)


3-10.あなたは養育費を受け取っていますか、それとも支払っていますか。(任意・単一選択)


3-11.あなたが支払っている/受け取っている養育費を月額で教えて下さい(任意・単一選択)


3-12.最初に別居・離婚を申し出たのはどちらからでしたか。(任意・単一選択)

3-13.どのような方法で離婚が成立しましたか(任意・単一選択)


3-14.別居・離婚直前のあなたの収入は、世帯収入のどの程度を占めていましたか。およその割合(%)を教えてください。(任意・単一選択)


3-15.別居・離婚直前のあなたと相手の一週間あたりの家事分担について、あなたのおおよその分担割合(%)を教えてください。(任意・単一選択)


3-16.別居・離婚直前のあなたと相手の一週間あたりの育児分担について、あなたのおおよその分担割合(%)を教えてください。(任意・単一選択)